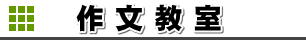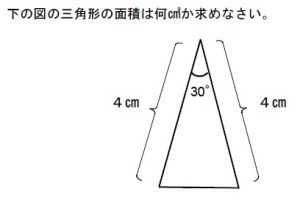「成績がすべてじゃない」
よく言われるこの言葉は、たしかに本当です。
テストの点数だけで人の価値が決まることは無いし、大人になってからも成績表を見せる場面なんてほとんどありません。
でもそうなると、こう考えてしまう中学生がいます。
「だったら、勉強しなくてもいいんじゃない?」
実はここに、大きな落とし穴があります。
◆ 勉強の価値は「点数」ではなく「力」にある
学校の勉強は、テストで評価されます。
だからつい、「点数=勉強の意味」だと思いがちです。
しかし本当は、勉強で身につくのは点数ではなく、
- 分からないことに向き合う力
- すぐに答えが出なくても考え続ける力
- 失敗しても立て直す力
- 筋道を立てて考える力
こうした、『一生使う力』です。
成績は、その力の「途中経過」をとりあえず数字で表したものにすぎません。
◆ 勉強をやめると、何が起きるのか
勉強をやめた瞬間に困ることは、正直ほとんどありません。
だからこそ、やめてしまいやすいです。
でも時間が経つにつれて、少しずつ差が出ます。
- 選べる進路が減る
- やりたい仕事に必要な条件を満たせない
- 数字やデータの話になると自信がなくなる
- 「考える役」ではなく「言われたことをする役」になりやすい
これは才能の差ではありません。
続けたか、やめたかの差です。
◆ 勉強は「将来の保険」でもある
中学生のうちに、将来の夢が決まっている人は多くありません。
むしろ、決まっていないのが普通です。
だからこそ、勉強は大切です。
勉強を続けていると、
「やりたいことが見つかったときに、挑戦できる状態」を保てます。
一方で、
「そのとき考えればいい」と勉強をやめてしまうと、
いざやりたいことが見つかったときに、スタートラインにすら立てないことがあります。
◆ 成績が伸びない時期は、やめどきではない
勉強しているのに成績が上がらないと、
「自分には向いていない」「意味がない」
と感じることがあります。
でも実は、
伸びる直前というのが、一番つらく感じる時期でもあります。
なぜなら、
分かることが増えてきたからこそ、分からないこともはっきり見えるようになるからです。
「こんなにも分からないことだらけだ」、と思ってうんざりした時が、分からないことがこれだとつかむことができた瞬間でもあります。
これがまさに、「成長している証拠」です。
◆ 最後に
成績がすべてではありません。
でも、勉強をやめてしまうと、自分の未来の選択肢を、自分で狭めてしまうことになります。
今の勉強は、いい高校、いい大学に入るためだけのものではありません。
- 「考える力」
- 「続ける力」
- 「逃げずに向き合う力」
それらを育てる、人生の基礎トレーニングです。
結果がすぐに出なくても大丈夫。
やめなかった経験は、必ずあとで自分を助けてくれます。
そして私も含め、周りの大人たちは、
成績だけを見ず、学び続ける姿勢そのものを大切にする
そうすべきだと思っています。