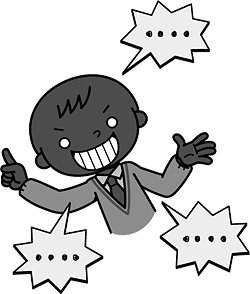最近、仙台二華中の話題をよく耳にします。
私の娘(小6)からは、友達との会話でも最近しょっちゅう話題に上るらしく、あの子もあの子も受けるんだって、とよく聞かされてますし、先日は生徒さんの親御さんからも、二華中の説明会に行ってきたんですがなどというお話もいただいたところです。
そこで今回は二華中のお話です。
先日(といっても昨年の話なのですが)、仙台二華中の校長先生のお話を伺う機会がありました。
塾向けのセミナーでのお話でしたが、いろいろと興味深いお話が聞けましたのでご紹介したいと思います。
まず仙台二華中についてですが、ご存知の通り「公立中高一貫校」です。つまり中学と高校がひと続きとなった学校ですね。
中学に入る時には入試があります。それも例年非常に高い出願倍率です。(狭き門となっています)
H25年:6.34倍
H26年:5.10倍
H27年:5.18倍
H28年:4.63倍
H29年:4.10倍
ここ数年はひと頃の過熱ぶりが収まってきて、受験者数も減少傾向にはあるようですが、倍率4倍というのはやはり合格難易度としては非常に高いものと言えます。
更に、二華中を受験する生徒さんはほとんど、各小学校のトップクラスの子たちなので、その中から合格を勝ち取ることはまさに至難の業と言っていいかもしれません。
必然的に、県内の優秀な生徒が集まってくる二華中ですが、中学に入る段階で入試を経験した二華中生は、高校(二華高)に入る時には入試がありません。これも二華中に入るメリットの一つです。
つまり、中・高の6年間という期間を使って、難関大入試に向けた勉強をきっちり、無駄なくできるということです。しかも、二華中の授業時間は他の公立中学と比べて3年間で、1教科当たり約100時間も多いそうです。
中3の時期にわざわざ高校入試に向けた受験勉強をしなくて済み、その代わり大学入試に必要な力をつけるための時間が多く確保されている、というのが大きな魅力なのだと思います。
ただ面白いことも校長先生は言ってました。
二華中の中3生は、他の公立中の生徒と比べるとどこか「幼い」と。それはおそらく、中3になっても同じ校舎に上級生(高校生)が存在することで、なかなかリーダーシップを発揮する機会が少ないことが原因ではないかとおっしゃってました。
公立中では、部活や体育祭などで下級生を引っ張っていくために嫌でもリーダーシップを発揮しなければならない時が来ますが、これはこれで人として成長するための貴重な体験となるはずです。
その機会が少ないことを二華中の課題と捉え、今後なんらかの方策を考え改善していきたいと最後におっしゃっていたことが非常に印象に残りました。
二華中受験について
もし本気で二華中合格を目指すのであれば、遅くとも小5の始めから受験に向けた勉強をする必要があります。小6からでは正直遅すぎます。
うちの子は小学校のテストでは毎回90点以上取れているから大丈夫、な訳がありません。
小学校のテストは基本が理解できているかの確認に過ぎません。最低限の知識として覚えなければいけない事なので、それが出来ているからと言っても何の受験対策にもなっていないと言っても過言ではありません。
二華中の試験は、「総合問題(100点満点)」、「作文(25点満点)」、「面接」の3つからなります。
この中の総合問題では、その名の通り総合的な視点から出題され、設問によって算数や社会の問題に別れていたり、同じ設問で理科と算数の知識を使って解く必要がある問題だったりします。
時事問題(最近のニュースや流行など)を題材にした問題も多く出されます。
そして、一度試験問題をご覧になれば分かると思いますが、どの問題もかなり長文の文章題です。
そのような問題を解く上で、絶対的に必要な力と言えば『国語力』に他なりません。
長い文章を早く読み取り、何を問われているのかを正確につかむ力。
そして解いた問題を、簡潔な文章で正確に伝える力。
この力がない限り、二華中合格は困難です。
「うちの子、計算は得意なんですが、ちょっと文章問題が苦手で」と言った時点で、残念ながら合格可能性はかなり低くなると思ってください。
普段から(できれば小学校低学年から)読書などを通じて、「語彙力」そして、「文章からイメージを作り上げる力」を鍛えておかないといけません。
読書が好きな子は勉強もよくできます。
いや、もともと勉強ができる子に読書も好きな子が多いだけなのかもしれません。ただどちらにしても、学力と読書には大きな相関関係があるのは事実です。
本を読まない子は、算数の問題の意味をすぐに理解できず、そこに書かれている数字だけを使って「かん」で計算をし出します。
最近習っているところがわり算というだけでわり算をするので、その時はいい点数を取ってきて親は安心するのですが、問題がランダムに出される学力テストや模試になるとボロボロの結果となります。
間違いなく、読書は国語力をあげるための大きな武器となると確信していますが、残念なことに、読書を始めたからといってもすぐに国語力が上がることはまずありません。即効性が無いのです。
ぜひ、今後二華中の受験をお考えの小学校低学年のお子さんをお持ちの親御さんには、”読書のすすめ”をなさっていただきたいと思います。
まだまだ小さいお子さんには、自分から本を読み始めるなどということはできないと思います。ここは親がどんどん出しゃばり、先回りして、本を読む環境を作っていただきたいと思います。
子どもの未来を見越す、「親の想像力」が試される時です!
読書をしない小学校高学年のお子さんは、すみません、二華中受験はきっぱりとあきらめましょう。
そして高校入試に間に合うように今から読書の習慣をつけ始めましょう。今からなら高校入試には十分間に合います。大きな武器を携えて試験に臨めるはずです。
小学生のみなさん、それぐらい”国語”は大切です。 算数や英語よりもです。